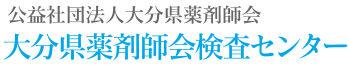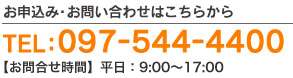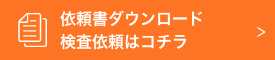よくある質問
- 検査料金の支払い方法は?
-
窓口で現金でお支払い、またはお振込となっております。
お振込みの場合は、後日結果書と一緒に振込用紙を送付いたしますので、指定口座までお振込をお願い致します。
- 自宅の井戸水を検査してみたい
-
一般的には10項目での検査ですが、より詳しく調べたい場合は全項目をおすすめします。
依頼方法はこちらをご覧ください。 - 採水容器はどのようにしたらよいですか?
-
事前に無料で採水容器を貸し出しいたします。(検査の内容により容器の種類や数量が異なります。)
検査によって、容器は違いますが、取り扱い説明書、下記ページ、または口答でお答え致します。
- 採水方法は?
-
検査によって、容器は違いますが、取り扱い説明書、下記ページ、または口答でお答え致します。
- 検体の持ち込み方法は?
-
当所へ直接お持ち込みいただくか、各市町村の食品衛生協会へのお持ち込みも可能です。
食品衛生協会へのお持ち込みの場合は、持ち込み日が限定されていますので当所または食協へお問い合わせください。
- 検査にかかる期間はどのくらい?
-
10項目検査で、7~10日の検査期間がかかります。全項目を検査する場合は10~14日の検査期間が必要です。
- 検査結果の見方がわからない
-
別途検査結果の見方をお伝え致します。検査書をお手元にご準備の上、お問い合わせください。
- 検査結果で不適となった場合、どのような対処をしたらよい?
-
個別にご対応させていただきます。窓口までお問い合わせください。
- 茶色い水が出るのですが…
-
色度の影響として考えられるのは、鉄、マンガンが影響している場合があります。
- 一般細菌、大腸菌が不適だった。飲めないのか?
-
そのまま生活用水(飲用)としての使用はお勧めできません。滅菌処理設備が必要となります。また、応急の対応としては煮沸処理をすることが有効です。
- 一般細菌が300以上出ているが、手洗い用の水としては使用可能だろうか。
-
すぐに症状が出るわけではないと思いますが、生活用水(飲用)に使うのはあまりお勧め出来ません。
- 色度と濁度はどう違うのか。
-
水道関係でいう「濁度」とは、水に混ざっている濁りを白色で見た時の濁りの程度をいいます。
「色度」とは、水に溶け込んでいる色調を黄色で見た時の色の程度をいいます。
これらは、水道水の「外観はほとんど無色透明であること」の要件を満たしているかを検査する項目です。 - 色度が高かった。原因は?
-
鉄、マンガンが高い可能性があります。もしくは、フミン質(土壌中の植物が微生物によって分解されてできる有機物)が多く含まれている可能性もあります。
鉄、マンガンを除去する装置を設置するか、活性炭でフミン質を取り除くか等検討された方がよいかと思われます。 - 営業許可の為の10項目の検査を行なったが、色度が5.7と不適合になった。温泉の近くにある井戸なのでどうしても色がついてしまうのだがどうしたらよいか。
-
営業許可で使う飲料水は10項目で適合しなければ許可はおりません。再検査をし続けるよりも、一度保健所に相談することをお勧めします。
- 雨が降った後に水が白濁する。原因を究明するために検査したい。
-
白濁要因として考えれれる金属として亜鉛やアルミニウムがありますが、断定できないので推測で検査することとなります。原因を究明するのは難しいので、保健所への相談をおすすめします。
- ポットに白や青の付着物がある。検査できるか。
-
白い付着物はカルシウムやマグネシウム、青色の付着物は銅の可能性が考えられます。付着物であればX線分析、水であれば上記の項目の検査をお勧めします。短期間で付着物がつくようであれば検査をした方が良いですが、そうでなければ一度様子を見てみてはいかがでしょうか。
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素が不適合
-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は土壌や肥料等、広く存在します。これらを多く含む水を摂取すると、主として乳幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ)を起こす可能性があるといわれています。通常の浄水方法では除去できないので、水道水とブレンドして基準値以下となるよう調整して使用する等された方がよいです。
- 亜硝酸態窒素が不適合
-
亜硝酸態窒素は硝酸態窒素に比べて極めて低い濃度でも健康に影響があります。塩素消毒をすれば硝酸態窒素となり、亜硝酸態窒素としては問題なくなります。
- 検査を依頼したい
-
食品検査は予約制になっています。
受入れの準備等がございますので、必ず1週間前までにご予約ください。
検査の内容によりましては、受入れができない場合もございます。
また、下記ページでも詳しく記載しておりますので、こちらもご参照下さい。
- パッケージに表示するために栄養成分検査をしたい
-
栄養成分表示セットがあります。
- 農作物の残留農薬検査をしたい
-
使用した農薬名がわかれば教えてください。当所で検査できる農薬であれば必要量等をお伝えします。
- 食品中の放射能検査をしたい
-
下限値によって必要量が異なります。まずはご相談ください。
- 検査に必要な検体量は?
-
検査する項目によって異なります。まずはご相談ください。
- 検体の搬入方法は?
-
要冷蔵の商品は、クーラーボックス等で冷やしてお持ち込みください。
- 検査にかかる期間はどのくらい?
-
検査の内容によって異なりますが、細菌検査が7~10日、残留農薬の検査が10~14日、栄養成分は10日~14日の検査期間が必要です。
- 個人で食器(ガラス製)を輸入して販売しようと思っていますが、検査が必要でしょうか。
-
食品衛生法では、食品のみでなく食品が直接接触する器具・容器・包装についても規制の対象としています。
材質によって検査項目が変わってきますが、輸入される予定の食器はガラス製のためカドミウムと鉛の溶出試験が必要です。
また、本格的に輸入する前に問題がないか確認をしておきたい場合は、一般検査として検体をお預かりして検査を行うことをお勧めします。
- ドレッシングを作っています。栄養表示が義務化となると言う話を聞きましたが何を記載すればよいでしょうか。
-
表示が義務となるのは「エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」の5項目です。
栄養成分表示は、分析値ではなく理論値での表示も可能となっていますが、表示と分析値との誤差が± 20%の範囲を超えた場合、食品表示法違反となりますので、一度分析することをお勧めします。
- 検査に必要な量はどのくらい?
-
検査する項目や定量下限値などによって異なりますが、目安としては、可食部で細菌検査(一般細菌、大腸菌など)は、100g以上、理化学検査(栄養成分やミネラルなど)は200g以上、残留農薬は200g~1kg以上、放射能検査は100g~2kg以上です。事前にお問い合わせください。
- パッケージに表示するために栄養成分検査をしたい。
-
2015年4月に新しく食品表示法が施行され、消費者向けの加工食品及び添加物への「栄養成分表示」が義務付けられました。
エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質、食塩相当量の5項目が必須です。
当センターでは、お客さまのレシピをもとに計算する方法と、食材そのものを分析して分析値を出す方法の二通りがあります。
用途や予算に応じてご希望の方法をお選びください。
- 賞味(消費)期限を設定したい
-
商品の特性を考えて、検査期間や検査項目を設定する必要があります。専門の職員が対応し、検査スケジュールを作成します。
- J-GAP審査のため、残留農薬の検査をしたい。
-
農場で使用している農薬を中心に検査すると良いです。使用している農薬名(商品名か有効成分名)をお知らせください。
- 稲作や畑作に使用する水を調べてみたい
-
農業用水の9項目の検査があります。昭和45年農林省公害研究会よりでており、法的拘束力はありませんが、水稲な正常な生育のために望ましい感慨用水の指標として利用されています。
- pH値の結果について、現場での結果値と持ち帰って検査した分析値が違う時があるが、なぜですか。
-
温泉の検査では、空気酸化の進んだ試料のpHを測定すると現地で測定した値よりも1近く変化することがあります。
一般的に低濃度のアルカリ性の温泉や鉄イオンを多く含む温泉、ガス成分を多く含む温泉では、現地と試験室でのpH変化が生じやすいと言われています。
- 依頼してから結果がでるまでどのくらいの時間がかかりますか
-
検査をご依頼いただいた後、お客様のご都合と当方の検査可能日に合わせて日程調整をさせていただきます。
調整後、決定したサンプリング日にお伺いし、現場で行うことのできない項目については持ち帰って検査します。
そのためサンプリング゙日から2週間前後の分析期間をいただいております。
- なぜ、10年に一度再分析が必要なのですか
-
温泉の成分は、時間の経過により徐々に変化が見られることが確認されています。
それぞれの地域等によって差異はありますが、源泉に含まれる代表的な成分である塩化物イオン、ナトリウムイオン、硫酸イオンを計測すると年を経過するにつれ、変動率が大きくなる傾向が見受けられ、一部の温泉では10 年後に大きな変化が見られたことから、入浴者の方々に対し現状の成分分析値を提供するため10年に一度の定期的な分析が義務づけられています。
- 自主的に10年以内で分析した場合、掲示の変更は必要ですか?
-
掲示の義務は「掲示内容が10年以内の分析結果に基づくこと」を求めるものであり、自主的に検査を受けた場合その都度掲示内容の変更を求めるものではありません。
ですが、分析の結果、成分等が大幅に変動していたことが明らかな場合には掲示内容を変更することが望ましいです。
なお、掲示内容を変更する場合はあらかじめ届け出が必要となっています。最寄りの保健所さんにご相談ください。
- なぜ、可燃性天然ガスの分析が必要なのですか?
-
温泉を利用するためには、温泉源から継続的に温泉水を採取することが必要ですが、地下から温泉水を汲み上げることにより温泉水への圧力が低下して、可燃性天然ガスが分離・放散することになり、災害を引き起こす危険性があります。
ですが、適切な施設及び採取方法によって安全な採取をすることが可能です。
施設及び採取方法の安全性を確認し、継続的に温泉水を採取するために可燃性天然ガスの分析が必要となっています。
- 温泉分析を依頼したいが手順はどうなっていますか?
-
まずFAXで依頼書をお送り下さい。
場所等の確認後、検査に伺う日時を連絡します。
また、下記ページでも詳しく記載しておりますので、こちらもご参照下さい。
- レジオネラ症とは?
-
レジオネラ症はレジオネラ属菌を原因として起こる四類感染症1)で、レジオネラ肺炎とポンティアック熱(インフルエンザのような熱性疾患)に大別されます。
主な感染経路は、レジオネラ属菌に汚染された人口水環境(浴槽水、冷却塔水、給湯設備など)のエアロゾル(水しぶき)を吸引することによるもので、ヒトからヒトへの感染はないとされています。
1) 診断した医師は、直ちに保健所に届け出なければなりません。 - レジオネラ属菌とは?
-
レジオネラ属菌はレジオネラ菌として分類される細菌の総称で、土壌や池、沼、水たまりなどの環境中に広く生息しています。
増殖に適した温度は36℃前後で、自然環境では20~42℃で生存します。
アメリカやヨーロッパにおいては、冷却塔等の空調設備から検出されることが多く、一方、日本では、公衆浴場や温泉、介護施設などの入浴施設から多く検出されます。 - 検査を依頼したい
-
当所でサンプリングする場合とお持ち込みの場合では、金額が異なります。
お持ち込みの場合は、事前に滅菌した採水容器をお送りいたします。当所、または最寄りの回収先へお持ち込みください。
また、下記のページに詳しく記載しておりますので、ご参照ください。 - レジオネラが検出されたときの対処法は?
-
レジオネラ属菌は、バイオフィルム2)(生物膜)中のアメーバ類等の原生動物へ寄生して増殖し、そこから水中に移行します。したがって、バイオフィルムを物理的、化学的に除去することによりレジオネラ属菌の供給源を絶つことができます。
2) バイオフィルムとは壁面や床面などに付着した微生物が増殖するとともに、粘性物質を体外に産生し、これらや微生物の死骸が混在、結合して形成されたもので、「ぬめり」と表現されることもあります。
以下に有効な手順の例を示します。
(1)責任者、清掃担当者など、チーム内で情報共有を図ります。
(2)清掃方法を確認し、再度、清掃を行います。塩素消毒をしている場合は、塩素濃度の確認も併せて行います。
(3)清掃後、再度、検査を行います。その際、補給湯(浴槽への注ぎ湯など)・水(加水している場合)の検査も併せて行うことが望ましい。上流へのさかのぼり検査を行うことにより、問題点を明確にすることができます。
(4)洗浄・消毒方法の見直し、浴槽壁等の損傷の有無の確認、付随設備の確認、記録簿による塩素濃度の確認、消毒装置の点検など、原因の究明を行います。
(5)対応の内容を記録しておきます。 - 換気の基準はありますか
-
換気の基準として、二酸化炭素は1500ppm以下であることが望ましいとされています。1500ppmを超えた場合は換気の強化を行うようにする必要があります。窓や欄間、入口の戸の開け方、開ける時間を検討する、機械による換気が行われている教室については、運転時間の検討や機械の整備点検を行うなど換気の方法を工夫してください。
- ダニが基準値を超えてしまいました。どう対処すればよいですか
-
基準値を超える場合は、電気掃除機を使用する、使用している場合は吸引力の低下に注意するなど掃除方法の見直しを行ってください。保健室の寝具には、必ずカバーやシーツを掛け、定期的に交換を行うなど使用頻度に注意してください。また、クリーニング等によるのり付けで布団の中からダニの出現を防ぐことができます。
- 現場検査と書類検査の違いは?
-
建築物衛生法が適用される施設のみ書類検査が可能になります。
- 高くて登れない為、屋上のタンクに異常が無いか気になっています。
-
梯子等を用いて屋上タンクに行くことが可能な施設であれば、検査員が伺い検査をすることが出来ます。
- 容量の小さい水槽でも検査お願いできますか。
-
簡易専用水道でなく、小規模の施設であっても検査可能です。その場合の判定基準は簡易専用水道施設と同様の判定基準が適応されます。
- 家のアパートの水槽の水が安全か心配なのですが。
-
簡易専用水道施設の検査の際に同時に簡易的な水質検査も行っています。
- 作業環境測定とはなんですか
-
労働者が働く環境において、人体に有害なものを取り扱う際に、暴露されていないかどうかを調べるためのものです。(労働安全衛生法第65条)
- 私の職場は作業環境測定しなくて良いのかが気になります
-
作業環境測定は、その職場で使用している物質や、職場環境(室内であるか屋外であるか)等により、測定の義務が発生します。当検査センターでは、作業環境測定士の資格を持った検査員が、調査から測定までを一括で行い、職場環境改善のお役に立っています。
- リスクアセスメントってなんですか
-
労働安全衛生法の改正により、平成28年6月1日から640の化学物質について、それらを取り扱う作業が、健康上問題がないかどうかを調査(リスクアセスメント)しなければならないこととされました。当検査センターでは、このリスクアセスメントについて各種ご相談に応じています。
- 検査料金は
-
現場を確認させていただき、採取場所の確認後にお見積りをご提出させていただきます。
- 塗装作業場で使用している塗料に含まれている化学物質について、作業環境測定の義務付けがあるのかわからない
-
作業環境測定士がご相談に乗らせていただき、調査いたします。そこで、作業環境測定の必要があれば、デザイン、サンプリング、分析を行って、評価するという検査の流れになります。
- アスベストとはなんですか
-
アスベスト(石綿)とは、天然鉱物の一種で、「耐久性」「耐熱性」等に優れ安価であった為に、建築物の建材として広く使用されてきたものです。しかし、このアスベストが原因で肺がんや中皮腫になることがわかり、日本では2004年にすべてのアスベストが使用禁止となりました。
- アスベストにはどんな種類があるの
-
アスベストは一般に「クリソタイル・アモサイト・クロシドライト・アンソフィライト・トレモライト・アクチノライト」の6種類のことを指します。当検査センターでは、これらすべての種類についての分析が可能です。
- どの建材を検査すれば良いの
-
建物に使われている建材の内、どこにアスベストが使われている可能性があるか判断するのは非常に困難です。当検査センターでは、国土交通省の認定した「建築物石綿含有建材調査者」資格を持った検査員が、現場調査から定性・定量分析までを一括して行います。
- 建物の解体をする予定なのだが、アスベストが使用されているか分からないので、現場に来て調べてもらうことはできるか
-
当センターでは実際にアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が現場に伺い、調査、サンプリング等を行うことが出来ます。また持ち帰った試料を分析して、アスベスト含有の有無を判定するという流れになります。
- 検査に必要な量はどのくらい?
-
下限値によって変わってきます。下限値10Bq/kgの場合は、可食部として100g程度から検査可能です。それより低い下限値まで見る場合は、2kg(2L)以上必要です。
- 食品以外の炭や稲わら等も検査可能か。
-
食品以外も検査可能です。お問合せ下さい。
- 海外輸出を考えているが、英文結果書は発行してもらえるか。
-
可能です。英文依頼書に結果書記載希望事項をご記入の上、ご提出ください。
依頼書のダウンロードはこちら - 地下タンクは設置していませんが、埋設配管だけでも検査できますか。
-
地下にタンクが無く、埋設配管のみの施設も検査の対象となります。
- 地下タンク設置からこれまで、特定の業者に依頼していましたが、廃業したので業者を探しています。
-
検査員が現場に伺い、見積りを出してからの検査になります。
- HACCP制度化って何をすればいいか。
-
衛生管理計画を作成して、実施記録を取ります。小規模事業者については、現在行っている衛生管理を見える化し、記録を残すという作業がメインになります。
2020年6月に施行されており、2021年6月には猶予期間が終了するため、2021年5月末までに作成しておく必要があります。
- 制度化されたら認証を取る必要があるか。
-
認証を取る必要はありません。新しく機器等を購入する必要もありません。
- 缶詰等、包装済み食品を販売するだけの場合はHACCPに沿った衛生管理は必要ないか。
-
温度管理の必要な食品の保管、販売を行う場合は対象になります。
- 衛生管理計画はどうやって作ればいいのか。
-
厚生労働省HPに、各業界団体が作成した手引書が出されていますので、そちらをもとに作成することをお勧めします。また、小規模事業者の方は大分県のホームページ””OITA HACCP””(https://oita-haccp.anshin-oishi.com/)からも作成可能です。
直接話を聞きたいという場合はご相談下さい。 - 競合他社との差別化を図るために衛生管理を強化したい。HACCP認証を取りたい。
-
専門の職員が対応いたしますので、お問い合わせください。